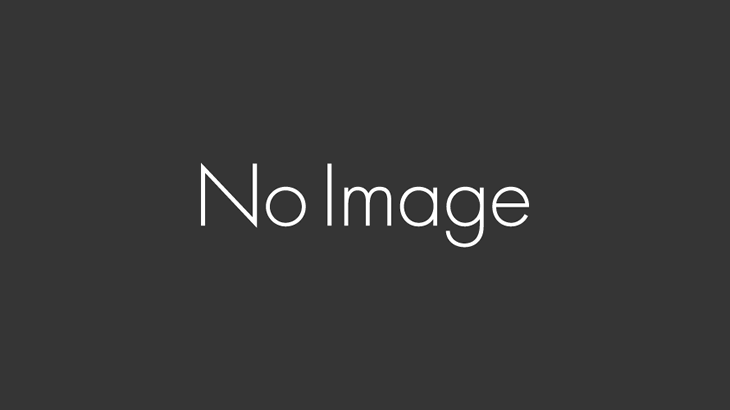
○×高校。葵の初めての国語の授業。教壇に立つ葵が「源氏物語」の一節を読んでいる。そんな彼女の姿を見つめる生徒のひとり・伊藤健次。その横の席にいる筈の夏川初音は、今日も学校を休んでいる。
授業が終って――、健次は葵に初音がどうしているか聞かれる。「夏川さん、新学期からずっと来ていないようだけど、伊藤くん、知らない?」 健次は、「知りません」と首を横に振った。
だが放課後、健次のケータイに初音からメールが入る。ラヴホで落ち合うふたり。エンコーで儲けた初音は、健次との若々しいHで燃えた。
事後、健次は新任の教師・葵のことを初音に話す。「お前、学校に来ないの?」 「学校なんてウゼーよ。ゼッテー行かねー」
ところが、それから暫くして初音が登校するようになったのだ。驚いた健次が尋ねると、なんでも初音の母・若菜にこっぴどく叱られたと言うのだ。「うちのママ、放任主義とか言って私に超理解あると思ってたのに、急に変わったんだよね。今度の先生は、すごくいい先生だから学校へ行きなさいって。怒ると恐いじゃん、うちのママ。だから、とりあえず学校に来てみたんだ」
実は数日前――初音の家に葵が家庭訪問に訪れていた。初めこそ「うちは放任主義ですから」とか「うちの子に限って」とか「母子家庭だからって、ちゃんと育ててます」とか言っていた若菜だったが、心を見透かす葵の不思議な力に次第に丸め込まれていったのだ。その上、Hまでご奉仕させられた若菜。オルガズムに達した時には、すっかり葵の言いなりになっていた……。
初音が変わったのは、葵が何かしたからに違いない。健次は、教壇で「源氏物語」を読む葵をじっと見つめた。
健次が公園でケータイを夢中になっていじっている。実は、小説家になりたい健次はケータイ小説を書いていたのだ。ふと、視線を感じて後ろを振り返ると、そこに葵が立っていた。「へぇ、伊藤くんにそんな趣味があったの。でも、なかなかうまい文章じゃない」 秘密を知られて顔を赤らめる健次。葵は、「将来は小説家? だったら、もっと本を読まなくちゃね」といろんな本を貸してくれた。
葵が貸してくれた文学小説は、どれも健次を刺激した。夢中になって本を読む健次。だが、それを医者である父・公次に見つかってしまった。「お前は、まだそんなことを! いいか、お前は医者になるんだ。医学部を受験するのに、文学などいらん!」 「でも、僕は小説家になりたいんだ。担任の先生も、いい文章を書くって……」
翌日、放課後の教室に公次が乗り込んで来た。「あんたか、息子をそそのかした女教師は!」と葵に向って言う公次。しかし、葵はひるまなかった――。
次の日、職員室に健次が飛び込んで来た。彼は、嬉しそうな顔で葵に報告した。「先生、お父さんが文学部に行ってもいいって言ってくれたんだ」 「そう。それはよかったわ」 それを聞いた葵は、優しく微笑んだ。
実はあの後――葵は、若菜にしたのと同じように、公次を丸め込み、いいなりにしてしまったのだ。放課後の誰もいない教室で、公次に濃厚な奉仕をさせる葵。
葵が来て以来、校内の風紀はよくなった。生徒たちの話す日本語も改善された。
しかしそれから数日後、葵が学校に来なくなった。病欠と言うことだったが、心配した健次は葵の家を訪ねてみる。すると、家の近くで喪服姿の葵を見つけた。すっかりやつれていた葵。健次が声をかけると、彼女は「恩師が亡くなった」と説明した。「等々力先生は、私にいろんなことを教えてくれた恩師なの。教師たる者、生徒への奉仕の心を忘れてはいけない。生徒が明るい未来へ向って羽ばたく為には、どんなこともしてあげなさい。それが、先生の教えだったわ」
そして、葵を女にしてくれたのも等々力だった。等々力とのセックスは、文学的だった。Hの最中、古典文学の一説が頭の中を駆け巡った。
話を聞き終わった健次は、葵に言った。「先生、学校に戻って来て。みんな、先生のことを待ってるよ」
健次に励まされた葵が、再び教壇に立っている。「源氏物語」の一節を読むその姿は、美しかった。